はじめに:認知症の理解が介護を楽にする
認知症の方への対応は、優しく接しても伝わらない時、つい心が折れそうになることも…。そんな時こそ、症状の特徴を知ることで、その方にあった対応方法が見つかることがあります。「認知症」とひとことで言っても、実際にはいくつかの原因疾患があり、それぞれに症状の現れ方や対応のコツが違います。ここでは、主な4つの認知症タイプを中心に、その特徴と対応方法を紹介します。
1.アルツハイマー型認知症(最も多いタイプ)
特徴
アルツハイマー型認知症は、最も多く見られるタイプで、認知症の約6割を占めます。
脳の神経細胞がゆっくりと壊れていくことで、少しずつ記憶力や判断力が低下していく病気です。
初期は「物忘れ」が目立ちますが、単なる加齢による物忘れとは違い、体験そのものを忘れるのが特徴です。
たとえば、「食事をしたこと」自体を覚えていないため、「まだ食べていない」と訴えることがあります。
進行すると、時間・場所・人の認識があいまいになり、日常生活に支障が出てきます。
やがて着替えや食事など身の回りのことにも支援が必要になることがあります。
よく見られる症状
- 同じ話を何度も繰り返す
- 物の置き場所を忘れ、「盗まれた」と思い込む
- 日付や季節感がわからなくなる
- お金の計算や買い物が難しくなる
- 夜になると不安が強くなる(夕暮れ症候群)
対応のポイント
① 否定せず、安心を優先
「食べてないでしょ」「忘れたの?」などの否定は混乱を招きます。
→ 「そうだったかもしれませんね。少しお茶でも飲みましょうか?」と受け止めて共感することで、安心感を与えられます。
② 見える・わかる環境づくり
記憶を補うためには、環境の整え方が大切です。
- 物の置き場所を決める
- よく使う物は見える場所に置く
- カレンダーや時計を活用して時間の感覚を支える
③ 焦らせず、ゆっくり関わる
急かしたり叱ったりすると、不安や拒否が強まります。
ゆっくりした口調で、一つずつ簡単な指示を出すと理解しやすくなります。
④ 昔の話を聞く
アルツハイマー型では、昔の記憶は比較的残っていることが多いです。
昔の趣味や家族の話を引き出すと、穏やかに会話が続くことがあります。
2.血管性認知症(脳梗塞などが原因)
特徴
血管性認知症は、脳梗塞や脳出血の後遺症によって脳の一部が損傷し、記憶や判断、感情のコントロールに影響が出るタイプです。
アルツハイマー型と違い、脳のダメージを受けた部分によって症状が異なるため、**「まだらな症状」**が見られるのが特徴です。
たとえば、昨日はスムーズに話せたのに今日は言葉が出にくい、着替えはできるのに食事の準備は難しい――といった日による波があります。
また、感情の起伏が激しくなったり、意欲が低下することもあります。
脳の損傷部位によっては、手足の麻痺や言語障害などの身体的な後遺症を伴うこともあります。
よくある症状
- 「できること」と「できないこと」の差が大きい
- 突然怒る、泣くなど感情の波が激しい
- 動作が遅くなる
対応のポイント
- その日の状態を観察する:調子の良い日にできることを一緒に行う
- 焦らせない:動作の遅れや言葉の詰まりにゆっくり付き合う
- リハビリや運動を継続:小さな成功体験が意欲を支える
3.レビー小体型認知症(幻視・身体症状が特徴)
特徴
レビー小体型認知症は、脳の神経細胞に**「レビー小体」という異常なたんぱく質がたまること**で起こる認知症です。
アルツハイマー型に比べると、**幻視(いない人や虫、動物が見える)**が現れやすく、意識がはっきりしている時とぼんやりしている時の差が大きいのが特徴です。
また、パーキンソン病に似た手足の震え、動作の遅さ、転びやすさなどの身体症状を伴うこともあります。
認知機能の波が大きく、「昨日はしっかりしていたのに、今日は混乱している」という状態がよく見られます。
よくある症状
- 「部屋に知らない人がいる」と言う
- 表情が乏しく、動きがぎこちない
- 夜間の混乱・夢を見て叫ぶなどの症状(レム睡眠行動障害)
対応のポイント
- 幻視を否定しない:「そんな人いないでしょ」と言うより、「怖かったね、どうしようか?」と安心を優先
- 転倒に注意:家具の配置や段差を見直す
- 薬の副作用に注意:抗精神薬に敏感なため、服薬管理は医師と相談
4.前頭側頭型認知症(人格変化・社会的行動の変化)
特徴
前頭側頭型認知症は、脳の前頭葉や側頭葉が萎縮することで起こるタイプです。
感情や社会性をコントロールする部分が影響を受けるため、行動や人格の変化が目立ちます。
比較的若い世代(50〜60代)に発症することも多く、「若年性認知症」として気づかれることもあります。
アルツハイマー型のような“物忘れ”よりも、性格の変化やこだわり行動が先に見られるのが特徴です。
よくある症状
- 怒りっぽくなる、暴言が増える
- 何度も同じ行動を繰り返す(同じルートを歩くなど)
- 食事のこだわり(甘い物ばかり食べる)
- 周囲への関心が薄くなる
対応のポイント
- 行動を止めすぎない:危険でない限り、同じ行動を見守る
- 環境でコントロール:興奮する要因(騒音・刺激)を減らす
- 家族のストレスケアも重要:相談機関やケアマネと連携を
5.混合型認知症も増えている
最近では、「アルツハイマー型+血管性」など複数の要因が重なるケースも多く見られます。
症状が多様になるため、一人ひとりに合わせた支援が求められます。
6.認知症ケアで大切なのは「人として向き合う」こと
どのタイプの認知症であっても、共通して大切なのは
「その人のこれまでの人生や思いを尊重すること」
認知症は「できないこと」よりも「まだできること」に目を向け、本人が安心して生活できる環境を整えることが介護の基本です。
まとめ:知識があると対応が変わる
| タイプ | 主な特徴 | 対応のコツ |
|---|---|---|
| アルツハイマー型 | 物忘れ中心・徐々に進行 | 否定せず安心感を与える |
| 血管性 | 症状がまだら・感情の波 | 状態を観察し焦らせない |
| レビー小体型 | 幻視・転倒・意識の波 | 幻視を否定せず安全確保 |
| 前頭側頭型 | 行動・人格変化 | 環境調整と家族支援が重要 |
認知症ケアに正解はありません。
しかし、特徴を理解しておくことで「なぜこうなるのか」が見えてきます。
その理解こそが、穏やかな介護の第一歩です。

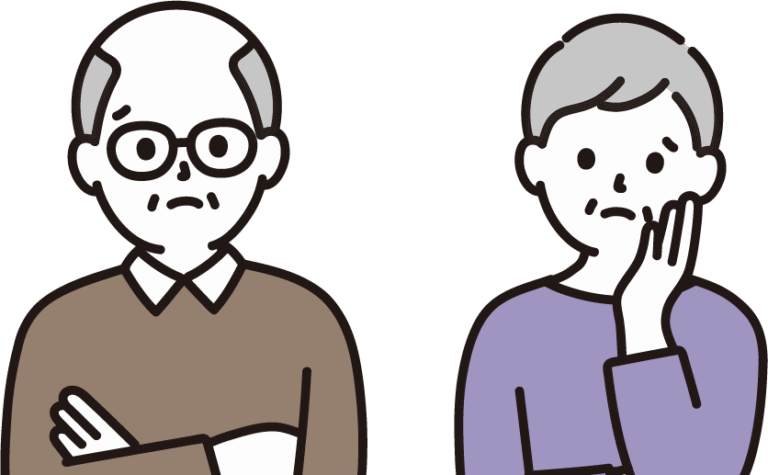


コメント