在宅介護を始める方へケアマネジャーが伝えたい認定調査の内容と心構え
こんにちは。ケアマネジャーkikiです。
日々、多くのご家族から「初めての認定調査が不安です」「どんなことを聞かれるのでしょうか?」といった相談をいただきます。
確かに、認定調査は在宅介護の最初の関門のように感じられるかもしれません。ですが、心配しすぎる必要はありません。調査の目的は「今の生活にどんな支援が必要かを見極めること」であり、できる・できないをジャッジして優劣をつけるものではないからです。
今回はケアマネジャーの立場から、調査の流れや実際にあったエピソードを交えて、心構えについてまとめてみます。
認定調査とは?
要介護認定を受けるために、市区町村の委託を受けた調査員がご自宅を訪問し、ご本人の心身の状態を確認する調査のことです。
調査の結果と主治医の意見書を合わせて審査され、「要支援1・2」または「要介護1〜5」といった介護度が決まります。この介護度によって利用できるサービスの範囲や量が変わってくるため、とても重要なステップです。
認定調査の流れ
調査員が訪問
市区町村または委託業者から事前に日程調整があり、当日は自宅に調査員が来ます。
本人への質問
可能な範囲で本人に答えてもらいます。認知症などで難しい場合は家族が補足します。
動作の確認
立ち上がりや歩行などを実際に試してみることもあります。
家族への聞き取り
本人が言いにくいことや日常生活の様子を、同席した家族が補足説明します。
調査で確認される内容
調査は大きく分けると次のようなポイントに整理できます。
1. 身体機能
- 起き上がる、立ち上がる、歩くなどの基本動作
- 食事や排泄、入浴の自立度
- 手足の動きや筋力の状態
2. 認知機能
- 今日の日付や場所がわかるか
- 会話のやり取りがスムーズか
- 記憶の保持や判断力の有無
- 徘徊や妄想などの行動の有無
3. 行動・心理面
- 昼夜の生活リズム
- 感情の安定度(興奮や落ち込み)
- 他者との交流の様子
4. 社会生活の適応
- 買い物や料理など家事の能力
- 金銭管理や薬の自己管理
- 外出の可否や交通手段の利用
5. 医療的なケア
- 点滴、酸素吸入、カテーテルなどの必要性
- 慢性的な疾患や定期通院の状況
調査員は質問するだけでなく、実際に動作を確認したり、本人の表情や会話の受け答えを観察したりしながら評価していきます。実際の動作をお願いしたり、ご本人の表情や受け答えの様子も観察します。
実例紹介
あるご家庭でのことです。
80代の女性が調査を受ける日、ご本人はとても張り切っていらっしゃいました。いつもはゆっくりしか立ち上がれないのに、その日は頑張ってスッと立ち上がり、「私はまだ大丈夫です」と笑顔で答えていました。
しかし、同席していた娘さんがすぐに補足してくれました。
「普段は立ち上がるのにかなり時間がかかります。今日は頑張っているんです。お風呂も一人では入れず、私が必ず付き添っています。」
その一言で、調査員は実際の生活像を理解してくれました。もし娘さんが補足をしていなければ、実際よりも軽く判定されてしまったかもしれません。
こうした場面に私は何度も立ち会ってきました。
調査の場では、利用者さんが元気に見せようとするのは自然なこと。だからこそ、家族の補足やケアマネの視点がとても大切なのです。
調査にのぞむときの心構え
1. 良いところを見せすぎない
調査の場では、本人が「まだ大丈夫」と頑張ってしまうことがあります。しかし、それでは実際の生活よりも元気に見えてしまい、適切な介護度がつかない恐れがあります。普段通りの姿を見てもらうことが大切です。調査が来るからと掃除を張り切る方もいらっしゃいますが、部屋も普段通りで大丈夫です。掃除が困難になっていることを伝える大切な情報です。
2. 家族が客観的に伝える
本人が答えられない部分や、日常での困りごとは家族がしっかり補足しましょう。
「週に数回転倒しそうになる」「夜中に何度も起きて徘徊する」など、具体的に説明すると伝わりやすいです。もの忘れや排泄のことなど本人の前では話にくいこともあるかと思います。そういった際は別室での聞き取りの意向を伝えたりメモに書いて調査員に渡しましょう。
3. 事前にメモを準備する
介護の困難さを当日うまく説明できないこともあります。
「食事に何分かかるか」「排泄の失敗はどのくらいあるか」など、日常の様子をメモしておくと安心です。
4. 恥ずかしがらずに正直に話す
排泄や入浴の介助など、話しにくい内容こそしっかり伝えることが重要です。ここを隠してしまうと、必要なサービスを受けられない可能性があります。
5. 主治医とも情報を共有しておく
認定には主治医の意見書も使われます。普段の診察で、介護に必要な部分を正直に伝えておくと、医師の意見書にも反映されやすくなります。
ケアマネジャーからのひとこと
在宅介護は、ご本人だけでも、ご家族だけでも成り立ちません。認定調査は「支援を受けるための入り口」です。
私がケアマネジャーとして関わってきたご家庭でも、実際の状態より軽い認定がおり必要なサービスを受けれないという相談は多いです。お忙しいとは思いますが、認定調査の際は立ち合いを希望していただいて、家族の視点で実際の状態を伝えれるようにしておきましょう。
介護は一人で抱え込むものではありません。調査の場でも、そしてその後の介護生活でも、ケアマネジャーは“伴走者”として寄り添います。どうか安心して、ありのままを伝えていただければと思います。
まとめ
認定調査は、ご本人やご家族にとって緊張するものですが、目的は「必要な支援を明らかにすること」。
- 良く見せようとせず
- 困っていることを具体的に伝え
- 家族やケアマネがしっかり補足する
この3つを意識すれば、調査は決して怖いものではありません。
在宅介護のスタートラインに立つ皆さんにとって、この情報が少しでも安心につながれば幸いです。

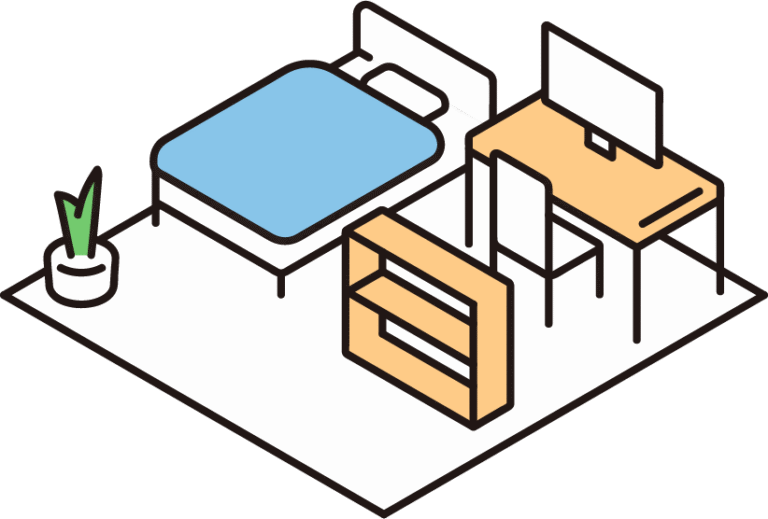


コメント